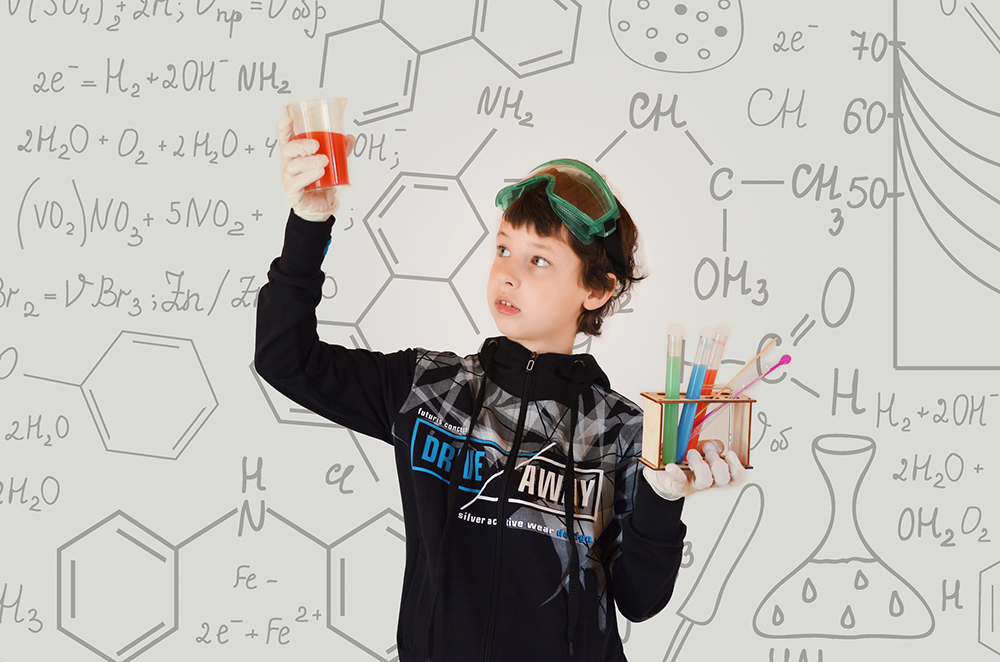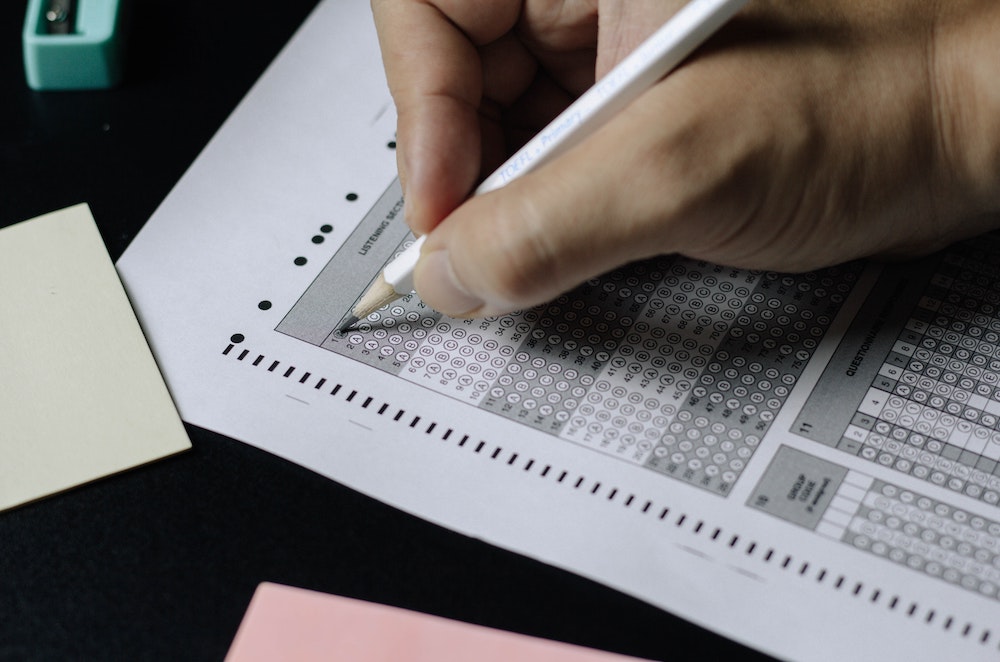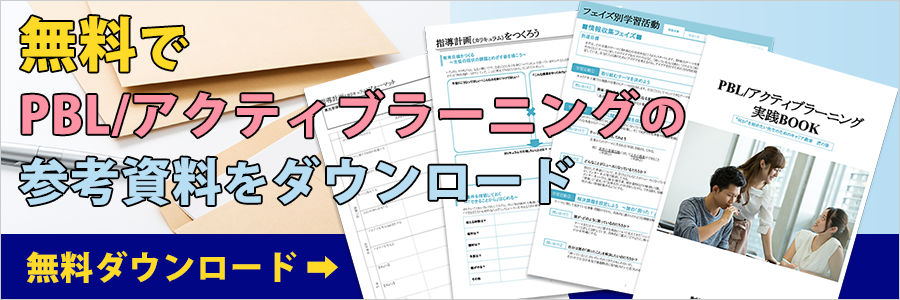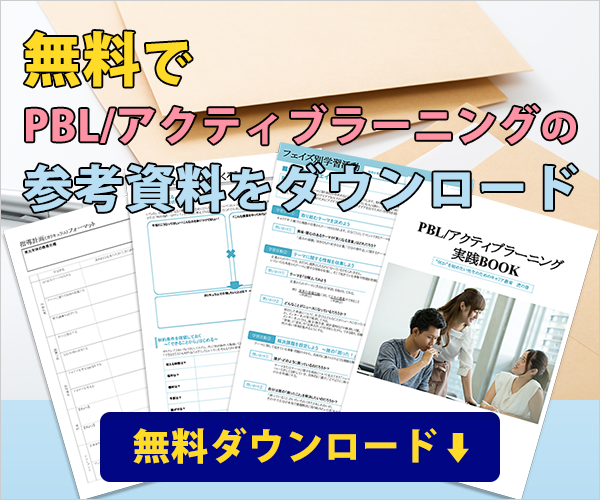理想と現実のギャップ
「生徒が自ら問いを立て、自発的に学びを深めていく」――。探究学習は、生徒の主体性や問題解決力、創造性など、これからの社会に必要な能力を育成することを目指しています。2022年度から高校で必修化された「総合的な探究の時間」(文部科学省、2018年発表『高等学校学習指導要領』によって全国の教育現場で実践が進んでいます。
しかし、その理想と現実とのギャップに悩む教員の声も少なくありません。この記事では、高校現場における探究学習の具体的な課題を明らかにし、限界を乗り越えるための現実的な方策について考えます。
探究学習指導の主な課題
時間的制約
文科省が提唱する探究学習のプロセスは、「問いの設定」「情報収集」「整理・分析」「まとめ・発表」と多岐にわたりますが、実際の現場では時間が十分とは言えません。多くの高校が週1コマ程度しか探究に充てることができず、受験指導や定期テストとの兼ね合いで削減されがちです。
例えば、1年間という限られた期間内でテーマ設定から調査、成果発表までを実施することが求められますが、実際には短時間の中で深掘りすることが難しく、表面的な活動にとどまることも少なくありません(文科省が提唱する探究学習のプロセスは、「問いの設定」「情報収集」「整理・分析」「まとめ・発表」と多岐にわたりますが、実際の現場では時間が十分とは言えません。多くの高校が週1コマ程度しか探究に充てることができず、受験指導や定期テストとの兼ね合いで削減されがちです。
例えば、1年間という限られた期間内でテーマ設定から調査、成果発表までを実施することが求められますが、実際には短時間の中で深掘りすることが難しく、表面的な活動にとどまることも少なくありません。
リソース不足
地域間や学校間の資源格差は深刻です。特に地方の高校では、企業や大学など外部の協力機関が近くにない、あるいは交通費がネックとなって現地視察や外部講師を招くことが難しいケースが多く見受けられます。
都市部では、地元企業や大学とのコラボレーションによる充実した探究学習が行われている一方、地方では予算の制約や人脈の限界により、実践の幅が狭まっています。
生徒のモチベーションのばらつき
探究学習では、生徒自身が主体的に問いを立て、自発的に取り組む姿勢が不可欠です。しかし、「何を調べれば良いか分からない」「探究活動に意義を見いだせない」といった生徒もいます。教員が過度に介入すれば主体性の醸成に逆行し、放置すれば学びの質が低下するというジレンマに直面します。
実際の現場では、生徒の関心の個人差が激しく、クラス全体の探究活動の質を一定に保つことが困難なケースも多いのです。
教員の負担増
探究学習では、生徒ごとのテーマや進捗状況が異なるため、指導や評価が複雑化します。また、探究活動の内容に応じた適切な評価基準を作成することも求められ、経験不足の教員にとっては負担が重くなります。
文科省の『令和4年度教員勤務実態調査』でも、探究学習の導入により教員の業務負担が増加していることが指摘されています。
課題を乗り越えるためのヒント
では探究学習を実行していく上での課題を認識した上で、どのようなことを意識して取り組めばいいのでしょうか。全てを一度に対応するのではなく、少しずつ実践可能な工夫を取り入れていくことが大切です。
時間の有効活用
授業時間が限られる場合、短期間で完結する「ミニ探究テーマ」を設けて段階的に経験を積ませる工夫が効果的です。例えば、1学期間で「問いの設定」と「簡易調査」、次学期に「深掘り調査」と「発表」と分割し、段階的な学習を設計します。
まだ生徒も教員も探求学習に慣れていない状態で壮大で難しい課題に取り組ませると、必要以上に手間と時間がかかってしまいます。「駅前にお店を作るとしたら?」など、身近かつ楽しみながら取り組めるテーマを用意しましょう。
リソースの工夫
前述した通り、特に地方の学校は東京などの都心部に比べると企業も少なく、協力してくれる外部のリソースに限界があります。民間企業や自治体が主催するコンテストに参加することも視野に入れてみてください。取り組む上での教材や取り組むテーマなどを提供してくれるコンテストも多いようです。
マイナビでは「マイナビキャリア甲子園」を主催しています。無償で教材や企業テーマをご提供していますのでぜひご参加ください。
チームビルディングを用いる
生徒のモチベーションのばらつきには万能の薬はありません。ただ、少しでも生徒間の差を縮めるためにも、チームビルディングを必ず導入しましょう。探求学習の導入で行うのと行わないのとでは大きな差が生まれます。過去にチームビルディングについて取り上げていますのでご参考になさってください。
教員間連携
探究学習の成功事例や失敗事例を共有するため、校内で定期的な勉強会や情報交換会を実施すると、ノウハウの共有が進み、孤立を防ぐことができます。ただ、そのほかの業務で多忙な教員を巻き込んでいくのはハレーションの原因にもなってしまいます。理想は、教員間の中で自然発生的に探求学習指導に意欲的になってくれることです。
前述した外部のコンテストに生徒が受賞をすると学校全体で活気になるため、ほかの教員の理解と関心を得られやすいです。ただこれは狙ってできるものではなく、日々の指導の積み重ねはどうしても必要です。ある程度耐えて忍ぶ過渡期も現実には起こり得ることをご了承ください。
いかがでしたでしょうか。学習効果を発揮すると生徒にとっても教員にとっても非常に学びの体験となる探求学習ですが、期待と裏腹に課題も大きいためそのギャップに苦しむ教員も多いのが実態です。
キャリア教育ラボではさまざまな記事を掲載していますのでぜひご参考になさってください。
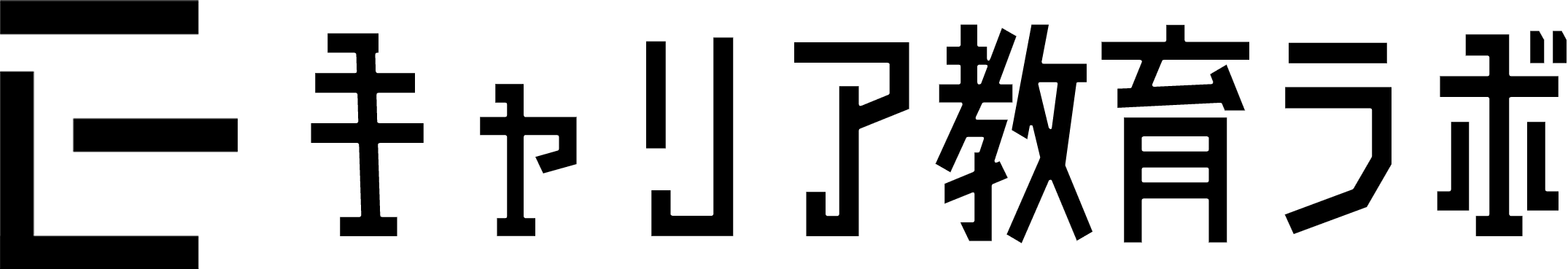

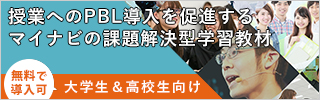
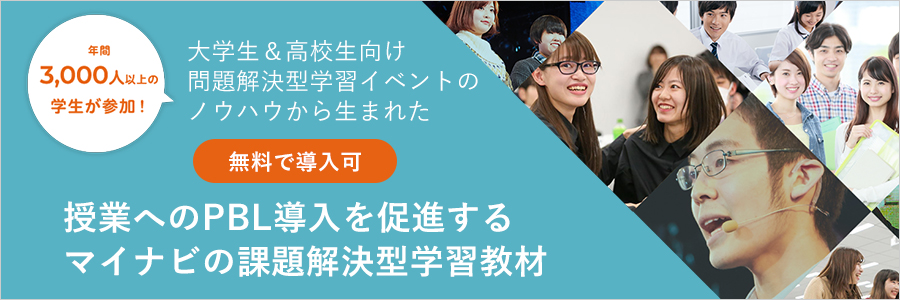
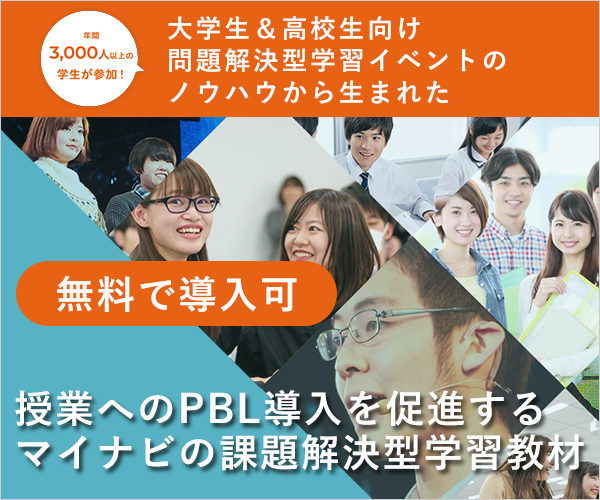
 LINEでシェア
LINEでシェア